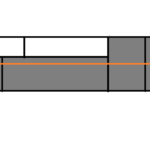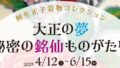みあです。
着物を着たら、風を通して片付けましょう。
着物をなおして次を待つ
着物を着たら、風を通します。晴天が続く日に2日ほど、湿気を飛ばして、目立つ汚れがないかよく確認。きれいにたたんで、次に着る時まで箪笥になおします。普段着は家で洗濯しますし、悉皆屋さんにお願いするような洗いには、出してもシーズンに1度。着たから出すというより、気になるものを見つけたらシミ抜きや洗いに出す、という流れのほうが多いですね。
着物を片付ける?片す?なおす(´▽`)
関西圏では、片付けることを「なおす」と言うことが多いようです。おみ足の短いお嬢パンダが過ごした街に住む私も、幼い頃より「なおす」と言ってきました。地域が違えば「なおす」が通じないことを知ったのは大学生の時でした。これも方言だったのか、とはじめて気づきました。片付ける?片す?なおす?他にもあるのでしょうね、きっと。
単衣の着物を着て、2日ほど風を通していましたので、箪笥になおしましょう。
着物をたたむ
着物を自分で着始めた頃、たたみ方がなかなか覚えられず、その度に本を開いたり動画を検索したりしていました。母がたたむところや、悉皆屋さんに出したものを受け取りに行ったときに見ているのに、いつもわからなくなる場所は同じでした。脇線を合わせるところです。
本などでは「本だたみ」と紹介されている基本のたたみ方です。
まず、衿を左にして、皺ができないように置きますよね。下前身頃を脇縫いできちんと折ります。で、その下前身頃の衽を折り返す。ここまでは良いのですが、その後が「あれ(゜-゜)?」となりまして。上前の衽を下前の衽に合わせて、さらに上前の脇線を下前の脇線と合わせる、という過程できちんとできない。
でも、幼い頃から母が着物をたたむところを見てきて、着物をたたむという一連の動作の中では、この部分が最も好きなのです。たたむ動作に好きも嫌いもあるのか?とお思いになるかもしれませんが(^^ゞ
上前の脇線の裾の部分と腰のあたりをつまんで、下前の脇線と合わせる動作が、洋服では見ないような動きで、しかもそれまでテレテレと広がっていた裾がその動作でピシっときれいに揃うのですから、小さい頃からこの動作を見ると「うわぁ・・すごいなぁ」と、なんだか不思議な気分になったものでした。
たたみ方のこの動作が好きで、きれいだなぁ、と眺めていたのに、いざ自分がたたもうとすると、なんだかうまくいかない。「なんで?おかしいな・・」と、その度に調べ直していました。
長年見ていたので手順はだいたいわかっているんだけれど、自分でたたんでいなかったので手が覚えていないのです。どこまで折り返すの?とか、脇線を合わせる前にきちんと衽を合わせないといけなかった・・とか。一度きちんと覚えてしまえば、なんということもないのですが。
衿をきれいに
ところで、着物をたたむ際、私が最も気を遣う部分は、衿です。衿と背縫いの周辺に皺が寄ったり凸凹のある状態で箪笥にしまい込むと、次に着た時にきれいに見えない。実は、何枚か変な皺が寄ってしまった着物がありまして。きっとたたむ時にきれいにできていなかったか、たとう紙に置く時にズレたとか、なのでしょうね。次に着る際に気づいたら少し鏝をあててみようと思います。この部分は、特に人目につくので注意しています。
どの箪笥に?
きれいにたたんだら、箪笥になおしましょう。
‥と言っても、我が家の着物用の箪笥は、実に4棹もあるのです。
祖母、母、私の3代の持ち物全てをあわせて、3棹の箪笥にみっちり詰まっていた状態(最も多いのは祖母のものですが)から、全ての着物と帯、襦袢を引っ張りだして、普段着用とそれ以外にわけ、数年にわたって、内容の把握と整理整頓、洗い張りやお直しに時間をかけて、わけがわからん、という状態はようやく脱しました。
今回着て、きれいにたたんだ着物は、格や季節によってわけた箪笥のうち、普段着着物の箪笥の単衣着物の引出しになおします。
先日の母の外出用に着物を選んだ際も、うそつき襦袢、裾よけ、着物、帯の一式を、すぐに出すことができるようになったことを実感(*´▽`*) やっとここまできたか、と感動すらおぼえました(^。^)
まだ改善の余地があるようにも思いますが、数を減らさない限り、現状がほぼ最適解でしょう。
そうだ、そろそろ夏物を着る用意をしておこう!
今年、夏物を真夏ではなく少し前に着ることにしようと決意した、ごきげん子猫